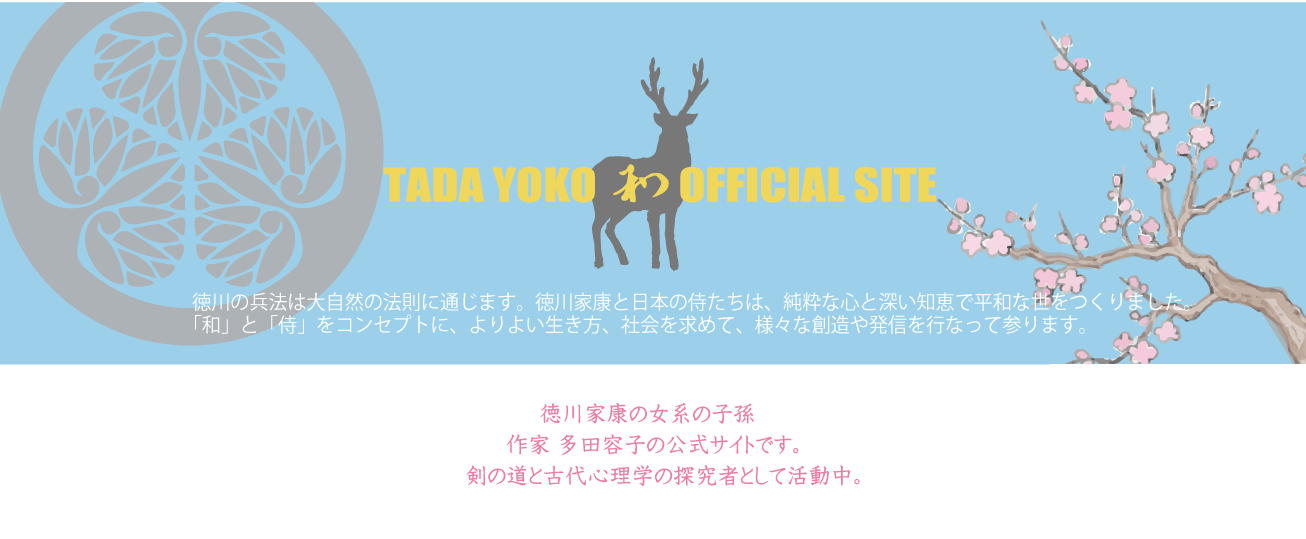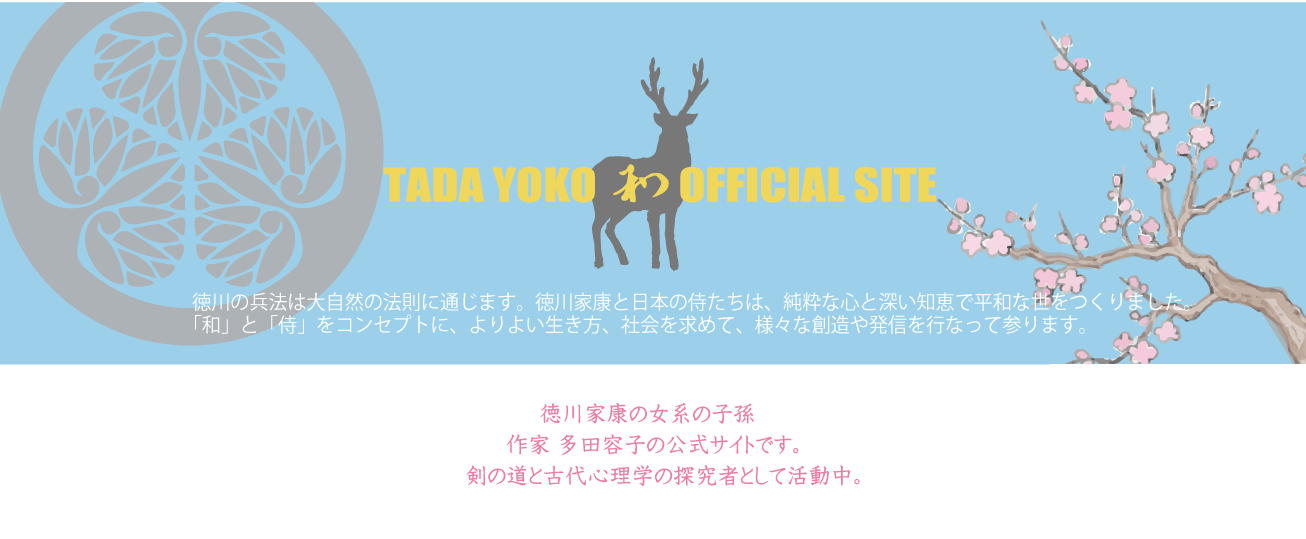【2023.8.22】
自立した人々による主体的な協力の時代──分野を超えて今を表現する
今日、2023年8月22日は何の日でしょう。
夏休みの一日だと答える人もいるでしょう。
伝統的な暦や吉凶などに詳しい人なら、一粒万倍日(一粒の種が大きく実る吉日)と言うかもしれません。世界情勢に関心のある人は、どこかで、ある大きな出来事が始まることを知っていて、注視しているところだ、と言うかもしれません。
どのような分野の人にとっても、大きな意味でも小さな意味でも、今に共通するキーワード。それは「自立」だと感じます。
これと似た意味で「主体性」という言葉も重要だと思います。
誰かに支配されたり、依存したりして生きる時代が終わるということです。
個人の話でいえば、まず、自分の人生は自分のものであるということ。
親のものでもないし、学校の先生のものでもないし、会社の上司のものでもないし、有名な専門家やアドバイザーのものでもないし、自分に投資してくれる資本家やスポンサーのものでもない。
こういうと、個人主義を奨励しているように思われるかもしれません。
しかし、個人主義というのはむしろ過去のものであり、日本では、戦後の昭和後期から急速に広まりましたが、その個人主義の考え方や行動様式が、今、崩れつつあります。
個人主義の社会というのは、個人の自由があり、個人の気持ちなどが尊重されて、とても魅力的なイメージがありました。
しかし、よく考えてみると、ある個人が自由に振る舞うことで、他の人に迷惑がかかるかもしれません。
利害が対立する個人の間では、喧嘩や訴訟などが起き、何かのきっかけで騒動や暴動に発展する危険性もあります。
他にも、大きな問題がありました。
個人主義は、人間を孤独に陥れたのです。
日頃、人に合わせて行動したり、面倒な付き合いをしたりしなくてよいのは楽です。が、何かあったときに困ったり、大事なことを誰にも相談できなくなったりして、とても心細い人生を歩むことになりました。
そんな孤独な個人は、会ったこともないような他人に依存するようになります。
健康の問題、心理的な問題、経済的な問題、法的な問題などなど……困ったときに、各分野の専門家の意見を聴くのです。
直接、専門家にアドバイスを求めることもありますが、まずは、新聞、雑誌、本、テレビなどで専門家が言っていることを頼りにして、物事を判断しがちです。
そういう人が、社会の中で多数派を占めると、これが世間一般の常識となります。
リアルな社会で人と会っても、皆、同じような考え方をもっているのです。
結果的に、自分の意見や考えを自由に言える場は減りました。
いわゆる同調圧力といったものがかかり、皆が空気を読んで、メジャーな流れに呑まれることになりました。
つまり、私たちは戦後、個人主義の自由な社会を謳歌しているといわれながら、実は、とても画一的で、コントロールされた社会に生きていたということです。
近年では、そのコントロールが息苦しいほどになってきました。
だから、個人が勇気をもって「自立」することが大事なのです。
少し困った時や迷った時、何でもすぐに外部の情報に頼らず、自分で考えてみる。解決しようと試み、工夫してみる。
そういった発想と姿勢が重要だと思います。
これは、何でも独りで解決しようと、頑なに自分の殻に閉じこもる、という意味ではありません。
人を頼るにしても、安易に、権威ある人や有名な人が言っている意見を採用するのではなく、誰に頼るかをよく考えたほうがよい、ということです。
困った時というのは、不安な気持ちや依存心が急激に高まって、冷静な判断がしづらいもの。そのため、できれば日頃、何事もない時から人間関係について真剣に考えておく必要があります。
自立の中でも、現代人にとって特に意識すべき課題は、精神的な自立だと思います。
これはかなり難しいことですが、本当に、自由にのびのびと自分の人生を生きるためには、極めて大切なことです。
「自立、自立」というと、独りというイメージが強くなるので、他の言い方をするならば、「主体性をもつ」ということです。
家族と生きていたり、友人と過ごす時間が長かったり、会社に属していたり……何らかの形で人と関わり、チームや組織で行動する人は多いでしょう。
その時に、ただ相手や組織に依存するのではなく、自分が主体的に、そのチームのために何ができるかを考えるのです。
例えば、あなたが若い学生だとして、親がいつも不機嫌で、ガミガミと説教ばかりしてくる、としましょう。
この時、親の意見を素直にきくか、または、反抗するか、無視して聞き流すか。
選択肢は、それくらいしかないと思うかもしれません。
しかし、これは子どもの感覚であり、親に依存している状態なのです。
もっと大人になって、自分が中心だという感覚で、親や家族の状況を観れば、おそらく考えは大きく変わります。
親は仕事が忙しくて、疲れているのかもしれない。仕事の関係や近所づき合いなどで、何かストレスを抱えているのかもしれない。
それなら、自分が代わりに家事を引き受けよう。あるいは、親の悩みを聴いてみよう。
このような新しい発想、行動が生まれてくるのです。
問題が親の側にあるのではなく、本当に自分が未熟過ぎて、親が「ありがたい説教」をしてくれている、という可能性もあります。
親は、将来の見通しも立たず、これといった目標もなく、家では家事もせず、ただの子どものように過ごしている息子や娘を見て、本気で注意しているのかもしれません。
これならば、とても自然なことです。
本人が、人生について真剣に考えておらず、自分の生活や人生に責任をもとうという姿勢が見えない。
そんなとき、親が子どもの行く末を心配し、叱るのは当然でしょう。
このような事態であれば、親の説教を「素直にきく」どころの話ではありません。
すぐにでも、自分のことを真剣に考えるべきです。
自分で考え始めれば、いろいろと試してみたいこと、知りたいことなどが出てきます。
すると、親との関係も変わるのです。
親に仕事や人間関係、家事のことなどを尋ねて、むしろ、いろいろなことを教えて欲しいと思うでしょう。
説教をされて、うるさい、などと言っているのはおかしい、と気づくはずです。
親は人生経験の宝庫であり、余ほどの悪人でない限り、誰よりも我が子のためを思ってくれています。
そういう人から助言を受けられるか、受けられないか。この差は大きいと思います。
親など、大人の知恵や力を借りるのは、早く一人前になるためです。
これは、自立するための主体的な学びと成長の期間であって、弱々しい依存ではありません。
たとえ自分が無知で、何かを教わる側であっても、主体的に取り組むことが重要です。
親も、子どもをただ可愛いと思い、手元に置いて甘やかし、自分のコントロール下に置き続けたい、といった煩悩から脱する必要があります。
精神的に自立し、家族全体や社会にとって何が大事かを考え、子どもを立派な大人にしなければなりません。
ここまで、親と子の関係を例に述べてきましたが、こうした関係性や構造は、様々な場面で見られると思います。
会社などの組織に依存し、上司に言われて嫌々、仕事をしている社会人もいるでしょう。
チームの同僚にガミガミと怒られて、反発し、対立してしまっている人もいるでしょう。
心が自立していて、物事に主体的に取り組めているか。
人生を自分の人生だと感じ、仕事を自分の仕事だと思って、自分の意志や判断で動けているか。
これは、年齢とはあまり関係がありません。
年齢的には大人でも、依存心が強い人はたくさんいます。
職場や家庭などに不満がある場合、本当の問題はどこにあるのか。
これを考えねばなりません。
まずは、自分に問題がないかをゆっくりと観てみることが大事です。
どれほど考えても、他の人に問題があるという場合は、その相手に改善を迫るしかありません。
例えば、職場に問題のある上司がいる。
自分だけでなく、多くの人がその上司の命令に疑問を感じたり、もっと違った、より良い意見をもっている。
そういう場合は、上司にただ反抗的な態度を見せるのではなく、真剣に、組織の行く末を考えるべきだと思います。
志の一致する人たちで集まり、力を合わせて上司に意見を言い、改善を図るとよいでしょう。その意見が素晴らしい、あるいは、まともな話ならば、聞き入れられるはずです。
どれほど言っても分からず、問題が続くようならば、また考えねばなりません。
その悪い上司から権力を奪う、というくらいの構想も、もたなければならないでしょう。
しかし、それが私的な権力争いになれば、組織が壊れかねません。
ですから、闘争にならないよう、皆で連携、協力して、圧倒的な多数派となってから、行動に移すのが得策でしょう。
個人個人が主体的に考え、協力する集団というのはとても強いものです。
「誰かが言ったからついていく」あるいは「こちらの派閥が優勢だと聞いたから、入っておく」といった、思考停止のような追従主義とは違います。
誰かの指示や命令を待って動く人が多い組織は、発想から行動までにタイムラグがあり、仕事が遅くなります。
何も考えていなかった状態から動き出すため、「よっこいしょ」感があるのです。
命令が伝達されるうちに、誤解が生じたり、本来の趣旨が変わってしまったりするケースもあるでしょう。
良いか悪いかも分からず、ただ有力な人についていくという人は、依存心だけでなく、恐怖心が強いのだと思われます。
とにかく、よく分からないこの世の中が怖い。だから、自分の保身ばかりを考えてしまう。
そのため、強そうな人や、ものをよく知っていそうな人についていこうとする。
しかし、それは自分を信頼していない生き方であり、自分の力を過小評価していることに他なりません。
偉い上司や専門家の先生が言っていることでも、よく考えてみれば、自分でも分かる、ということは、けっこうあるものです。
社会には問題が山積していて、組織の長たちの権力や、金持ちたちの資金や、専門家の知恵や膨大な量の情報をもってしても、解決などできていません。
もしかすると、自分で考えたほうが早いかもしれないのです。
少なくとも、自分の身近な問題については、自分が最も詳しい事情通なのですから、自分や近くの仲間で解決できる可能性があります。
本やネットの情報などは、その時に活用する補助的なものと考えたほうがよいかもしれません。
思考や活動の主体は、あくまでも自分なのです。
自分で思いついた解決法や具体策というのは、「ぜひ実行してみたい!」と強く感じるものです。
パワーが湧き、実現力も高くなるでしょう。
現代人は、何かに依存したり、メジャーとされる考え方に追従することが多かったため、自分の考えで行動してよいのだろうか、と不安に思うかもしれません。
初めは、判断を誤ったり、方向性は正しくても具体的な部分で失敗したり……いろいろな困難にぶつかる可能性もあります。
しかし、そうしたリスクを冒すことが、まさに自立であり、危険を乗り越えてこそ自信がつくのです。
危険を冒したり、難しい問題を解決したりするうちに、気づけば立派な大人になっている。
以前は大ごとだと感じられた問題が、今は大したことではないと思える。
自分の歩んで来た道や、成長ぶりを誇ることができる。
これが人生の恩恵であり、素晴らしさだと思います。
今、多くの人が孤独を感じ、他の人や社会から認められたいと願っているようです。
認めて欲しい、認めて欲しいと思い、懸命にアピールしつつ、なかなか思うような喜びや満足感が得られずに悩んでいます。
しかし、本当の大人は、人に認められても、認められなくても仕事をするものです。
それは他の人の気持ちや評価を無視する、という意味ではありません。
いちいち認められなくてもよい、ということです。
誰かを助けていたり、世の中の役に立っていて、いつかは必ず認められる。そんな信念や確信のようなものがあるから、一時的な評価が気にならないという意味です。
そういう状態に至れば、あまり不安を感じなくなるでしょう。
次はどんな良い事をしようか。
今度は、どんな問題を攻略しようか。
こういう考えや姿勢になり、知恵も湧きやすくなります。
漠然とした不安に心を支配され、いつも悩んでいるのに新たな行動ができず、結局は思考停止とあまり変わらない。
こんな人生は、本当に辛いものです。
ぜひ、自分の力を信じて、自立した人生を歩むべきだと思います。
精神的に自立した人間が、主体的に集まり、協力し合えば、多くの問題が解決できるでしょう。
それは、独りのリーダーや一部の権力者に、盲目的に従う全体主義ではありません。
個人が、我がままな子どものように、自由気ままに自己主張をする個人主義でもありません。
皆が主体的に行動し、自由に知恵を出し合い、助け合う。
そんな社会を作るということです。
こうした考えで、筆者は様々なコンテンツを書いていきます。
大きな柱は、以下の三つです。
「自然和合エニアグラム
心を癒し、あなたを成長させる古代心理学」
「日本式サムライ経営術」
「剣の神と鹿と正道古流の復興」
いろいろなジャンルのことを、なぜ同時並行で書くのか、と疑問に思う人もいるかもしれまません。
しかし、すべての分野、テーマはつながっています。
経営術や組織運営には、心理学が不可欠です。
心理学を本当の意味で深く学び、我がものとして身につけるためには、精神的な自立や主体的な修行が必要です。
そうした修行を経て、精神的に成熟した人物が、組織や人を動かせば、非常に良い仕事ができるでしょう。
剣と日本人の心も、切っても切れない関係にあります。
伝統的な日本の知恵や心を学ぶことは、精神的な自立の役に立つと考えています。
日本には、千年単位でつながっている、素晴らしい歴史がある。
いつも変わらない心の軸がある。
その実感が得られれば、人生観は大きく変わる可能性があります。
先人達が、日本の未来のために何をしてくれたのか。
そこには、どのような心があったのか。
これを知れば、自分たちが将来を見据えて何をすべきかも、見えてくるでしょう。
剣は、戦いをいかに制するか、という問題について私たちに教えてくれます。
経済的な戦いに晒されている人々にも、剣の神や昔の剣豪たちは、様々な知恵を与えてくれることでしょう。
以前、「広い世を観て、新しい社会を作る 不変の法則『相似』」などで書いたように、この世界には相似の法則があります。
ある小さな形や構造が、そのまま拡大されて、大きな社会や世界に当てはまるという理があるのです。
兵法(剣術)にも、相似がありました。
一対一の剣術は「小さき兵法」と呼ばれましたが、その理をよく知り、拡大すれば、国を治める「大なる兵法」にもなるのです。
これは、江戸時代に将軍を導き、大目付として政治を行なった柳生宗矩が、実際に用いた兵法です。
心理学にも相似の理は当てはまると思います。
個人が精神的に自立し、成長すれば、その集まりである家庭やコミュニティー、職場の組織などが、もっと成熟したものとなる。
個々の家庭や組織が変われば、町や村や市、都や道府県なども、もっと主体的に発展するようになる。
各地方が活気づき、自立するようになれば、国も変わる。
エニアグラムなどの古代心理学はもともと、国を治めるようなリーダーが学んだものです。
この深い知恵が、社会全体を良くするのに、役に立たないはずがありません。
心理学は、個人の内面を掘り下げるものでもありますが、決して個人のものではありません。
自分の内面を観れば、いろいろなことに気づき、自分の心を成長させることができます。
その結果、日頃の言動などが改善され、周りにも影響があります。
自分を知ることで、人間の心がよく分かり、他の人をよく観たり、社会についてより深く洞察したりすることも可能になります。
もし、自分のためだけに心理学を学んだとすれば、それを人間関係でうまく活用することはできないでしょう。
心理的な問題を個人の中だけで論じることは、実質、不可能です。
すべては、つながっているのです。
私たちは決して孤独ではありません。
これは、ふわふわしたイメージや、偽善で言っているのではありません。
現代人の多くは、自分で農業をしなくても、毎日、食べ物が得られています。
自分で家を建てたこともないのに、エアコン付きの家に住んでいたりします。
非常に多くの人に、助けられて生きているのです。
ただ、話す相手がいなかったり、一緒に過ごす人がいなかったり、分かり合える人がいないと感じたり……様々な理由で孤独を感じているだけです。
それは一種の錯覚であり、見方や行動様式を変えれば、解決可能な部分が多いと思います。
そのための鍵は、自立して、主体的になることです。
主体的な意識で、他の人々と協力し合うことです。
誰かが優しくしてくれたり、声をかけてくれるのを待っている、という姿勢ではなく、自分から人に優しくし、温かい言葉をかけましょう。
何か面白いことはないかなあ、と、文句を言うばかりではなく、自分自身が何か面白いことや、将来が楽しみになるようなことをしましょう。
誰かから認められたい、と願いながら、なかなか認められないのはなぜか。
それは、私たち自身が人の働きを認めていないからかもしれません。
食糧を得るにも、ネットで見て、ボタン一つで買って、届くだけ。
農家の努力や苦労を認めて、お礼を言いに行く人などほとんどいないでしょう。
むしろ、買ってあげている、という意識の人も多いように感じます。
様々な産物を適切に管理し、整理したり、箱に詰めたり、冷やしたり、運んだりする人々。
その過程で使う場所や機器、車、道路などを造っている人々。
彼らに直接、労力に見合うだけのお礼をしたり、敬意を払ったりする人は稀でしょう。
自分が他の人を認めず、お礼も言わず、偉そうにして、楽に過ごそうとしている。
それで、自分の仕事や努力だけ認めてもらおう、と考えても難しいと思います。
精神的に自立している人は、自給自足の生活をイメージすることができます。
すると結果的に、自分がどれほど多くの人に助けられているかを悟るのです。
社会の人々に、自然とありがたいという気持ちが湧き、お礼を言ったり、労をねぎらったり、優しくしたりしたい、と思うようになるでしょう。
そして、主体的な取り組みが始まります。
すでに、そういう気持ちで生きている人も、かなりいると思います。
だから、世の中は変わってきたのであり、そうした小さな積み重ねが、そろそろ目に見える大きな変化となって現れてくる時期。
それが今だと考えています。
今、必要だと思うこと、役に立つだろうと思うことを、分野や形を問わずに書いていきたいと思います。
今、浮かんだ旬の思いや考えをお伝えしたいのです。
近年、不思議な同時性や同調性が注目され、「シンクロ」という言葉をよく聞きます。
例えば、あることについて考えながら、ふとテレビをつけたら、ちょうどそのテーマの番組が放送されていた。
町を歩いていると、ちょうど最近、気になっていた言葉が、店の看板や広告などに書かれていた。
こうしたシンクロ体験は、吉兆ともいわれ、テンションがあがる人もいるでしょう。
ただ、これは、実のところそれほど特殊なことではない、ともいえます。
シンクロ体験は、様々なものがつながっているということに「気づく」体験です。
つまり、気づかないところでも、実は、非常に多くのものがつながっている。
世にはシンクロや相似形が溢れている。こう考えてよいでしょう。
シンクロや相似形の発見が、日常的な体験、感覚となれば、直感や洞察力が高まるでしょう。
自分が今、考えていることを、地球の反対側でも誰かが考えているかもしれない。
そう思って世界の情報を見ていると、本当にそういう人がいた。
しかも、そういう人は一人や二人ではなく、非常に大勢いた。
自分と同じような問題意識をもち、世界を良くしたいと思っている人が、実は数え切れないほどいた。
こんな嬉しいことも、有り得るのです。
だから、今という瞬間を大事にしなければなりません。
頭や心に浮かんだことを、文章化するにはどうしても時間がかかります。しかし、そのタイムラグをなるべく減らしたいと考えています。
細かいところでは、失敗や拙い部分などもあるでしょう。
しかし、大きな方向性を示し、それに共感する読者の皆さんが、主体的にコンテンツを活用して下さることを祈っています。
皆で力を合わせて、この社会をより良くしていきましょう。
|